「硬筆書写技能検定試験」の2問目に出題される楷書と行書の部分の勉強方法について書きます。
以前の記事で、試験「第2問目」で注意した点について記事を書いたんですが、今回はどのような事に気を付けて勉強したかについて。
このやり方で、ペン字検定(硬筆書写技能検定試験)2級に一発合格できたので参考にしてみてください。
2級までは独学でいけます。
五つの語句(10文字)を書く問題
まず実技の二問目はどういった問題かというと、枠内に五つの語句(計10文字)を縦書きで書く問題です。
枠の大きさは決まっているのでその中にバランスよく丁寧な字を書いていきます。
3級と2級では楷書と行書の二通りで書く必要があります(1級はこれに草書が加わります)。
書写検定の試験は字の美しさはもちろん、バランスも大事で、スペースの余白をどう使うかも見られます。
例えばこの「2問目」では字が大きすぎても小さすぎてもいけないし、かといって、余白が変に開いてしまったり字が詰まってしまっても良くない。
では実際にどうやって勉強をしていったらいいかということを説明します。
文字の大きさを気にせず練習してみる
上にも書いたように、本番では枠内にバランスよい大きさで漢字を書かないといけません。
しかし、日々の練習で字をキレイに書く訓練をするうちは、とにかく大きさを気にせずに自分の書きやすいサイズで書く練習をしていました。
何でもいいんですけど、例えば無地の自由帳に書くとかがいいですね。(コピー用紙は万年筆で書いた時滲んでしまったので微妙です)
「キレイに書くこと」と、「字の大きさを気にすること」、を同時に意識して練習するのは結構ハードルが高いです。
なので最初のうちは自分が書きやすい大きさでとにかく整った形を練習する事に重点を置きました。
実際に試験と同じ大きさの枠内で練習するのは慣れてきてからでいいです。
ひとまず整った字が書けるように練習を重ねる。
テキストを開いて気になる漢字をひたすら探す
はっきり言って、出題される可能性のある漢字は膨大にあります。
もちろんどの語句(漢字)が出題されるか全くわかりません。
なので問題集も結構書いたし他の字も描きたいな〜となった時は、目に付く漢字はとりあえず書いて練習をしてみる、という事をやっていました。
この場合ももちろん字の大きさは気にせずおもむろに書く、といった感じですね。
しかも問題集には問題は載っているけど、模範例が載ってないような場合が結構あります。
そういった時は三位字典(楷書・行書・草書が載った字典)を参考にしてどんな形で書けばいいのかな、と調べていました。
SNSで上手い人の字を参考にする
上でも話したように、問題集には、問題は載せているが模範例がない練習問題がけっこうあるんですね(これまじで個人的に結構厄介で、せめて問題に対する模範例くらいは全部載せてほしい)。
模範解答が無ければ、その字をどう書けばいいのかわからず、練習ができません。
字典を持っていればそれを活用すればいいですが、持っていない場合もあると思います。
そんな場合は、SNSを利用して上手い人の字を参考にするのが一つの手。
Twitterやインスタグラムでは手書きで書いた字を写真にアップしている人がいるので、それを参考にできます(僕は実際にTwitterを利用しました)。
勉強期間
他の記事でも書いてますが、勉強をやり始めたのは試験の4か月前。
試験は6月だったんですが、2月ごろから意識して勉強を始めたと記憶しています。
と言っても、毎日コツコツ練習していたわけでもなく、気が向いたときに練習するといった感じ。
限られた時間の中で、どれに重点に置きながら練習するかを考えなければいけません。
そのなかでも僕はこの【第2問目】に一番時間を使いました。
なぜかというと理由は単純で、楷書と行書を同時に両方練習できるから。
他の問題ではもちろん、楷書や行書で書く問題があるのでこの設問がきちんと書けるようになればほとんどの問題に対応できます。(準1級、1級は草書体の実技があるのでちょっと別の話)
書写検定の独学のやり方ついて
個人的な感覚では2級までは独学でも十分行けると思います。
ただ勉強のやり方、というか、どの問題の練習に時間を割くかで勉強時間が大幅に変わってきます。
今回説明した「第2問目」は基本となる楷書、行書が同時に練習できるのでいい勉強になります。
そして次に、苦手となる設問や理論問題に手を付けていけばいいと思います。
理論問題は、ひらがな・カタカナの元となる漢字や部首といった覚えれば確実に点が取れるところがあります。
他の受験生も確実に点を取ってくる設問でもあります。
理論問題で出るひらがなの元の漢字の記事も参考にしてみてください。
楷書と行書が練習できる第2問目は重要、あとは苦手な問題と覚えたら確実に点が取れる問題をしていく。
ぼくは実際にこの進め方で勉強しました。
もちろん人によって勉強の進め方はそれぞれありますが、勉強の進め方を迷ってる人にはおすすめです。
ペン字検定おすすめのテキスト
やみくもに練習してもペン字検定に合格するのは難しいです。
なぜなら設問ごとにどのように字を書けばいいのかポイントがあるからです。
個人的に、おそらく受験生のほとんどが知っている「合格のポイント」、もしくは2021年に発売開始された「公式テキスト」で勉強することを勧めます。
書写検定用の問題集や参考書は種類がホントに少ないのでこの辺りを押さえておけば間違いありません。
3級用↓
1・2級用↓
公式から唯一のテキスト

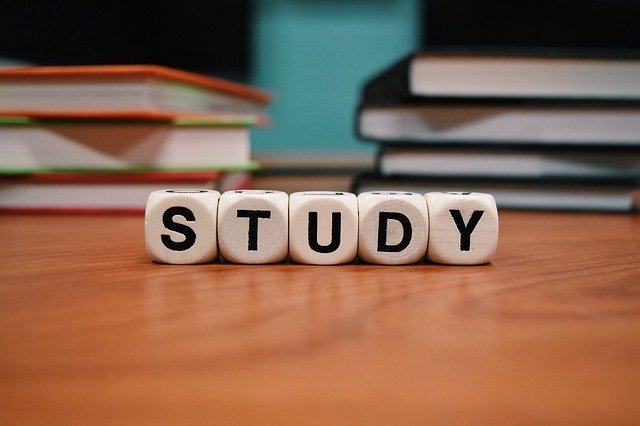
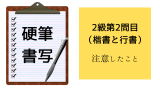





コメント