独学で行政書士試験を受けると決め、勉強始めて半年ほど経過しました。
今回は、現在私が何の教材を使って、どうやって勉強をしているのかを話します。
行政書士試験を独学で目指すっていう人は案外いるんじゃないだろうかと思うので、この辺りを話して試験までの経過をリアルタイムで残しておきたいと思います。
基本書を2回目を通した
900ページある基本書を2回ほど目を通しました。
期間は2か月ほどをかけました。
法律とはなんとなくこういうお話があるんだな、というレベルで読みました。
1回目では、1文を2,3回繰り返し読まないと言っている意味すらもわからない状態。
理解できない文章がいかにストレスたまる事か笑
途中いかに無理やり理解したつもりになって自分を騙すか、で進めていきました。
2回目では書いている言葉の意味は1回目よりもわかってくるのですが、読んだところを全く思い出せない状態。
読み終わって何を読んだのか言葉にして説明ができない。
でも2か月前よりは自分の中にある知識が何か変化したのはわかる。
問題集の行政法3回目の解いたときに正答率が8割程度に上がった
連続して3回同じ問題を解いたら正答率が格段に上がった事に自分でも驚きました。
大半はイメージで覚えているだけで、肢別ごとになぜこの肢が×なのか、というのはわからないとしてもふんわりと理解できているという状態にまでもっていけました。
行政法をメインに解き始めた
行政書士試験の配点は、行政法と民法の配点が圧倒的に高いんですよ。
なので私は試験まで残り8,9か月ある段階で行政法を中心に勉強をしています。
基本書を2回目を通した後に、問題集の民法と行政法を1度ずつ解きました。
この後、もう一度民法の問題を一から解きなおすのか、はたまた憲法を解き始めるのか、悩みました。
その時にネットで色々調べていた時に、行政法の勉強を重点的にやるのが良いという情報を目にし、行政法をさらに2度通しで問題を解くことにしたんです。
見開き2ページで1問ある問題集で、行政法だけでも240ページあったのでかなり時間はかかりましたが、集中して行政法のみをやりましたね。
行政書士試験には法令科目という出題形式があって、「憲法」「民法」「行政法」「基礎法学」「商法」と5つの分野から出題されるんですが、「行政法」はこれら244点分の内112点分出されるので結構なウエイトを占めてる。
「行政書士」と名前にも行政ってあるしやっぱり行政法を手抜きして合格はダメじゃんってことに気付いた。
独学の勉強にとって本が頼り
たとえわけわからない事がテキストに書いてあっても何回も何回も読んで、あ、こいつこの事言ってたんか、となるまで読むしかない。
というくらいにテキストだけが頼りになります。
というか本が先生。
独学の弱点。誰も簡単に説明してくれない。
テキストは基本的にカチカチした文章で説明してるんです。
自分なりに「これはこういう事なのか」と、かみ砕いて理解するしかない。
受験者数が多い試験はやっぱりテキストの種類も豊富
ここ数年の行政書士試験の受験者数は4万人ほどいるらしく、国内にある資格試験の中で受験者数の多い部類の試験となっている。
| 2022年度 | 47,850名 | 5,802名 | 12.13% |
|---|---|---|---|
| 2021年度 | 47,870名 | 5,353名 | 11.18% |
| 2020年度 | 41,681名 | 4,470名 | 10.72% |
| 2019年度 | 39,821名 | 4,571名 | 11.48% |
| 2018年度 | 39,105名 | 4,968名 | 12.70% |
ようは、行政書士試験用の参考書や問題集の種類は結構いっぱいあるって事ですよね。
私たち独学者にとってテキストだけが頼り。
そりゃあプロの講義を受けて行政書士試験の合格を目指していく方法がいいには決まっています。
そして受かりやすいに決まってる。
わかりやすい言葉で重要なところだけを教えてくれるんだから独学より合格に近づくのは明らかですよね。
でも私は独学を選びました。
なぜなら、それは、、独学のほうがお金がかからないから笑
これだけ。
独学の最大にして最強のメリット。
※(心の声:そりゃあお金があれば講座速攻でポチるよね。)
世の中にはユーキャンとかTACとか、有名な講座があります。
独学の一番のメリットは誰が何と言おうとやっぱりお金ですね。
講座を受けたり予備校に通うとなると数万円~と、ある程度の金額が必要になります。
お金がある人は迷わず講座を受けましょう。
時間をお金で買ってください。
1冊を完璧にするか、何冊も使って勉強するか
高校生のころ、大学受験のためによく友人たちと本屋に行ってました。
今考えたら、勉強のモチベーションを保ちに本屋に行ってたんでしょうね。
お店に行くたびに次から次へと参考書や問題集を買い、ほとんど手を付けずに次の本を買う、、、
の繰り返し。
1冊のテキストを完璧にするのが一番いい勉強方法だと当時思っていましたが、それがなかなかできないんですよね。
ついつい新しい本に手を出したくなる。
買ったら勉強している気になる錯覚。
1冊を完璧にするというのは似たような問題であれば必ず解けるということ。
ブレない知識が定着しやすいのではないでしょうか。
その反面、1冊のテキストまたは問題集だけで勉強することが本当に効率的なのか、という疑問もある。
たくさんの本で勉強するメリットは色んな種類の問題や知識に触れることが出来る。
行政書士試験なんかは過去問に似ていない問題も出題されている印象が強い。
そんな試験にはたくさんの知識に触れた方が良いのではないだろうか、と思うわけです。
私はインスタで行政書士試験受験者の方たちを拝見するんですが、みんな結構たくさんのテキストを使っている印象があります。
インスタ見てると購買意欲が刺激される。
私は勉強5,6か月目の現在、少ないテキストで勉強を進めていますが、そろそろ次の問題集を買おうと検討しているところ。
民法と行政法に関しては持っている問題集の8割くらいは取れるようになってきたからそろそろいいんじゃないだろうかと。(←言い訳)
というか、教材が少ないとなんか心細いというか不安になってくるというか、そんな気持ちになってきたんです。
今は肢別問題集が欲しい。
だってみんなこれ使ってるんですもん笑
そんなにいいのか肢別問題集。
(→※結局この肢別問題集書いましたがめっちゃ良かった)
五肢択一問題集じゃだめなのか?この半年間五肢択一しかやってきてない。
五肢の中から1つを選ぶ感覚を鍛えるべきじゃないのか?と思っていたけどみんな肢別使うんですよね。
みんなが使ってるならいいんでしょうね、きっと。
独学者たる者、教材だけはけちらず買う事にします笑
一緒に頑張りましょう!

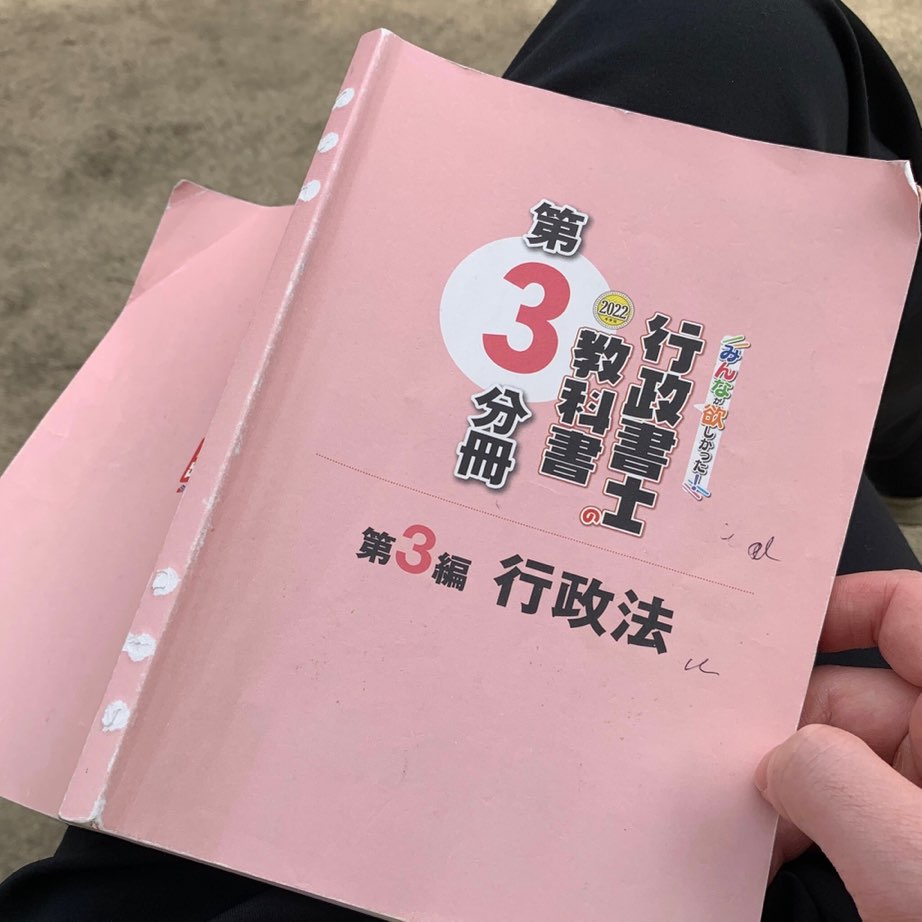




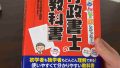
コメント