30年間理系人間として生きてきた私ですが、突然法律の試験である「行政書士試験」を受けることに決めました。
現在私は会社員なんですが、大学も会社も理系一色なので、法律なんて一切勉強したことありません。
こんなリーガルど素人の私が1年間独学で勉強したらどうなるのか、どれくらいやれるのか、というのを自分の身で実験し、皆さんにお伝えしていこうと思います。
このブログは、今まで趣味で硬筆書写検定を受けたりする美文字練習ブログとしてやってきましたが、資格つながりで行政書士試験ブログとしてもやっていこうと思います。
行政書士試験合格ブログを目指したい。
何か資格を取れば人生が変わるんじゃないかと思ったのがきっかけ
例にもれず私も普通の一会社員です。
「あ~会社行きたくねえ、やめたい。。」と毎朝目を覚ました瞬間から思います。
今の状況から抜け出すために、明るい未来のために何かやってないと不安でたまらない感情が大人になってからずっと心の中にありました。
何の取柄もない私のような人間が何か人生を変えようとしたときに思いついたのが「勉強」だったんです。
そんなに簡単じゃないとわかっていても、今の状況が変わるかもしれないなら再び勉強にかけてみる価値はあるんじゃないかと思ったのです。
国内には資格試験が山のようにありますけど、簡単には取れない国家資格が何か取れたら人生が変わるかもしれない、と。
(高校採用試験を長年受けている弟が勉強しているのを見て自分も何か勉強したいな~と思ったのもきっかけでした)
行政書士試験の勉強始めて約5か月で感じた事
たしか、受けようと決意したのが2022年の8月、参考書を買ったのが9月だったと思います。
この記事を書いている現在、2023年の1月後半なのでだいたい5か月がたちました。
で、今感じているのは、、正直言って1年じゃ結構本気でやらないと受からないな、ということです。
ネット上で行政書士試験に「半年で受かったぜ!」とか、「8か月でいけました」とかあるけど、正直自分には無理だと思います。
どこまで信じていいかわらないけど、噂では合格まで800時間~1000時間必要とかって言われてますが、1年間365日勉強したら平均で3時間すれば合格できる計算になる。
5か月間平均1時間くらいしか勉強してない僕私の感覚では、最低でもそれくらいの時間要るんだろうな、という感じです。
短期間で合格できた人はかなり詰め込んで勉強した、もしくはセンスのある、どっちにしてもただただ凄い人です。
法律の文章は初学者にとってとっつきにくい
私は大学が理工系、会社もそっち系の道に進んだので法律とは無縁の人生を送ってきました。
だからなのか、ホントに最初の数週間は文章の意味が全く分かりませんでした。
何を言ってるのかがまるで謎でした。
小説を読むのが好きなので、文章なんか楽勝だろと思っていましたが、間違いでした。
ここで挫折もありえましたけど、まあ勉強って最初はそんなもんだろうということで現在に至っています。5か月目。
最初の1か月は900ページもある超大作の教科書を眺めた
「眺めた」と書いたのは決して大げさではなく、「読む」というには言いすぎなほど全然理解できないまま900ページが終わりました。
私が買った基本書(勉強の中心になるテキスト)は900ページありましたが、他の出版社の本もだいたい同じくらいの分量があります。
必死こいて読み終わったのはいいものの、当然1か月前の内容なんて何も覚えていませんでしたね。
3か月目にようやく問題集に触れてみた
11月くらい(勉強開始3か月目)からやっと問題集を買い、「民法」と「行政法」と呼ばれる分野を一通り解き始めました。
この民法と行政法という範囲が、試験全体の6~7割程度を占める重要な単元だということで、そこだけをがむしゃらに解く日が始まりました。
問題集には民法行政法合わせて200問くらいの分量があって、一通り解くのに1カ月もかかりました。
やっぱり文章が理解できず、段々「学生時代やってた勉強の辛さってこういうものだったな、つら。。」っていう記憶が蘇ってきた時期でしたね。
問題2周目でも特に変化は感じなかった
問題集は反復練習してなんぼだと巷で謳われているのでとにかく2周目に突入。
2周目は1周目ほど時間はかからなかったものの、文章理解に時間がかかり、1か月前解いたはずの問題がほとんど初見に見えてしまうという錯覚に陥りました。
人間の記憶の曖昧さ(私だけでしょうか?)というものを思い知らされる出来事でした。
それでも、「前に進むんだ」という、心にまだ存在している闘争心で1日に80ページ進んだ日もありました。
今現在考えているのは、「100%理解できなくても問題をガンガン解いて進めていく」のがいいのか、「じっくり一つ一つ、問題を確実につぶしていく」のがいいのかという悩み。
個人的な意見は、はっきりわからなくてもガツガツ問題を進めていくのがいいのかなと思いますね。
基本書と同様、どれだけじっくり読んで理解しても、どうせまた忘れていると思う。
それならスピード重視で何周も解いた方がいいと思う派です。
じっくり深く解く1回より、理解は浅くてもスパスパ何周も解くほうが結果として最終的には覚えがいいのではないだろうか。
と思う。
どうでしょうか、勉強論について是非ご意見ください。
サラリーマンしながらの資格勉強は大変
昭和の香りがプンプン漂っている私の会社は、いまだに全員が朝から会社に出勤して残業してなんぼの昭和スタイルを貫ぬく会社。
もちろん仕事中にテキストを開くとかいった裏技ができません。
なので平日は出勤のバス車内とか電車の待ち時間に待合室で隙間時間を使って勉強するしかないのです。
働きながら家事育児しながらの合格者はほんとみんな凄いとしか言いようがありませんね。
以前(2017年,2018年)FP3級と2級に一発合格できた経験があるので、今回もある程度勉強すればいけるだろ、と思っていましたが、今回は本気でやらないと受からない事を勉強3か月目くらいにして薄々悟りました。
「ブログ書く暇があったら勉強しろよ」
この記事読んで思いませんでしたか?
「お前合格するの大変やて思うんだったらブログとか書いてないで教科書開けよ」と。
この記事書きながら思われてそうだな~と感じました。
いや、本当にその通りだと思います。
自分でもバカだと思います。
ブログとか書いてたら普通に1時間とかいくし、その1時間あったら問題10問くらいはいけたやろ、と。
これは完全な息抜きですね。
毎日毎日テキスト開いてたら血の通った人間味のある文章を書きたくなってしまったんです。
最近本屋に立ち寄ったら好きな小説家の新しい文庫が出ていて、今それ読みたいんですよ。
教科書より全然そっち読みたい、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ただ、一発で受かりたいんです。
久々にブログ書いて楽しかったです。
勉強に疲れたらブログ書こうと思います。
受験生の仲間のみなさん頑張ろうね。

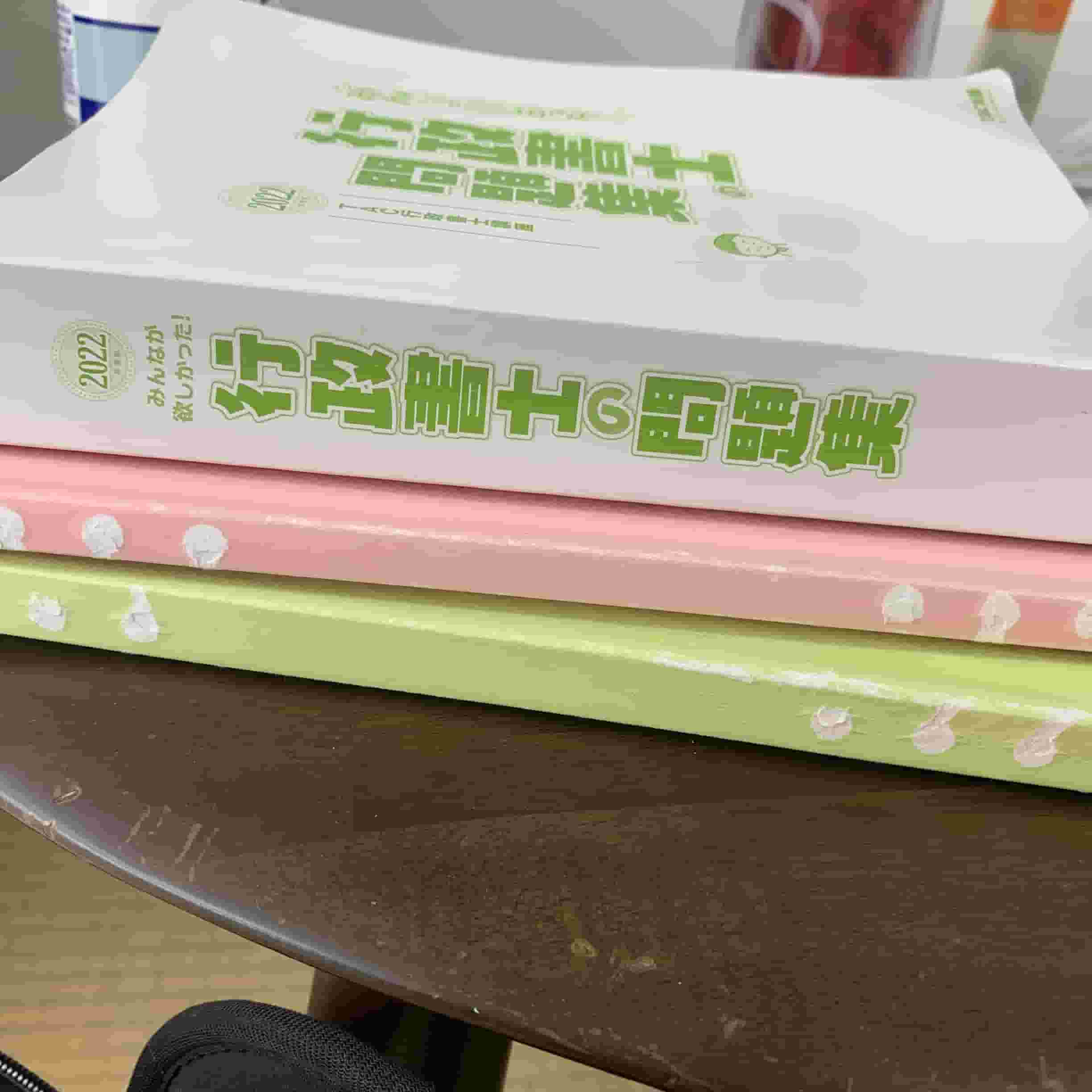






コメント