資格試験や入試の勉強をする時はやっぱり過去問を解いて勉強するのが王道。
書写検定の試験も例外ではなく、過去問を解いて勉強するのが合格するためには必要になります。
過去問が載っている問題集は種類は少ないものの、実際に売っています。
ただ、他の資格試験(例えば簿記とか英検とか)と比べると受験者数も少ないのでどこの書店に置いてる物ではありません。
実際私も地元の本屋になかったので楽天とAmazonで購入しました。
近くに大型の本屋が無い場合はネットで注文するのが良いでしょう。
書写検定を受けるのに過去問は必要?
私が受験した感覚から考えると、字がどれだけキレイに書けるようになっても過去問を解いてないと合格するのは難しいと言えます。
その理由は各設問ごとにポイントや書き方が違うからです。
また、書写検定の理論問題は暗記で解ける問題が出題されるので出題傾向を掴むには過去問に触れる必要があります。
問題形式が決まっているので、試験を受けるまでに過去問を解いて試験慣れしていきましょう。
書写検定の過去問はどこにある?
先ほども触れましたが、他の資格試験などは結構色んな参考書や問題集が書店で売られていたりしますが、
そもそも書写技能検定の場合、市場に売られている過去問題集はあまり多くありません。
それ程大きくない書店には書写検定関連の参考書や問題集が置いてない場合がほとんどです。
元々出版されているテキストの種類自体が少ないのが現状です。
ですが、少なからず過去問題を手に入れることはできます。
「日本書写技能検定協会」の公式ホームページで公開
公式ホームページでは各級の問題例と解答例が1回分無料で掲載されています。
こちらに載っている例題ははっきりと「過去問」とは謳ってないですが、かなり実際の出題に近い問題が載せられています(はっきりと断言はできませんがほとんど過去問と傾向が類似している感じ)。
なので過去問を解く感覚で勉強することができます。
ただし、各級1回分だけしか載っていないので、他の問題も練習してみたい人にとっては物足りなく感じるでしょう。
また、Web上で見るだけ(もしくはページを印刷して解く)しかできないので、実際の検定試験と同じ大きさで書く練習がしにくいため、これだけを中心に検定の勉強をしていくのは少し難しいです。
「日本書写技能検定協会」の公式ホームページで販売されている問題集
書写検定を主催している検定協会のホームページでは、先ほど紹介した掲載された過去問のほかに、過去問題が実際に売られています。
硬筆・毛筆ともに、過去1回分だけが載ったものと3回分が載ってあるものが売られています。
書写検定は年3回試験が開催されますが、比較的最近出題された過去問分を購入することができます。
試験に出題された実物の試験問題なので、最も試験本番に近い形で練習することができるでしょう。
公式ホームページでは本番の試験で使われる練習用紙も販売されているので、より試験と同じ感覚で勉強しやすいです。
紙質は練習する上で意外と大切で、試験で使おうとしているペンと解答用紙の相性が合う合わないがあります。
ぜひ一度試験用用紙で練習する事をおすすめします。
「硬筆書写技能検定 合格のポイント」
個人的に勉強するのに一番最適だと思ったのがこの「硬筆書写技能検定 合格のポイント」です。
私自身が試験勉強で使ったのもこのテキストでした。
過去の問題がふんだんに掲載された問題集です。
模範解答のほかに、合格するためのコツやポイントが書かれています。
この問題集を見れば、キレイな字が書けるだけでは書写検定に合格するのが難しい理由がわかるはずです。
問題毎のコツやポイントがそれぞれ丁寧に書かれているので実際に点数を取れるような実践的練習ができるようになっています。
もちろん実技問題と理論問題両方が載っているし、級によっては理論問題で出題される旧字体・書写体・草書体も載っているのでこの一冊だけでもかなり勉強が出来ました。
しかし、掲載されている問題すべてに解答例が書かれているわけではないので、載っていない字については自分で調べる必要があります。
手元に辞書などがあれば便利です。
「合格のポイント」は解答用紙にミシン目が入っていて切り取れるようになっていたので練習しやすかったです。
試験を受けるなら一度は目を通しておきたいテキスト。
おそらく硬筆書写検定を受ける人はほとんどの人が使っているんじゃないかと思います。

中古の問題集は既に書き込まれている場合があるので購入の際は新品をおすすめします
過去問は試験問題の雰囲気を掴むためのもの
過去問では実際の試験ではどのような形式の問題が出題されたかがわかります。
また、模範解答を見て、例えば行書の書き方はどういう風にすればいいのか(行書の書き方も一種類ではなく様々ある)を確認したり、
理論問題で点数が取れそうな設問や苦手な設問を自分の中で把握する時に過去問を活用しましょう。
ただ、特に実技問題の場合にはどの字が出題されるか範囲が広すぎてもちろんわからないので、過去問だけではなく、他の参考書や美文字練習本を使って色んな字に触れることが大切です。
「【硬筆書写検定】この本で書写検定一発合格できた|試験勉強で使ったおすすめのテキスト3冊」
↑私が実際に試験勉強で使ったテキストについてまとめました。
3級~2級を受ける時に役立つテキストはこの3冊です。
過去問を上手く利用して勉強すれば誰でも3級もしくは2級に合格できますよ。

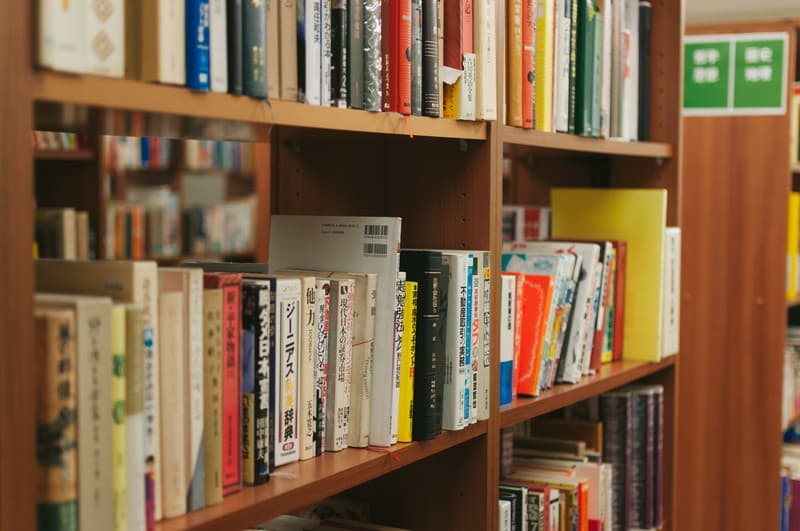






コメント